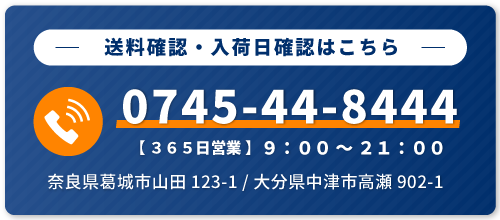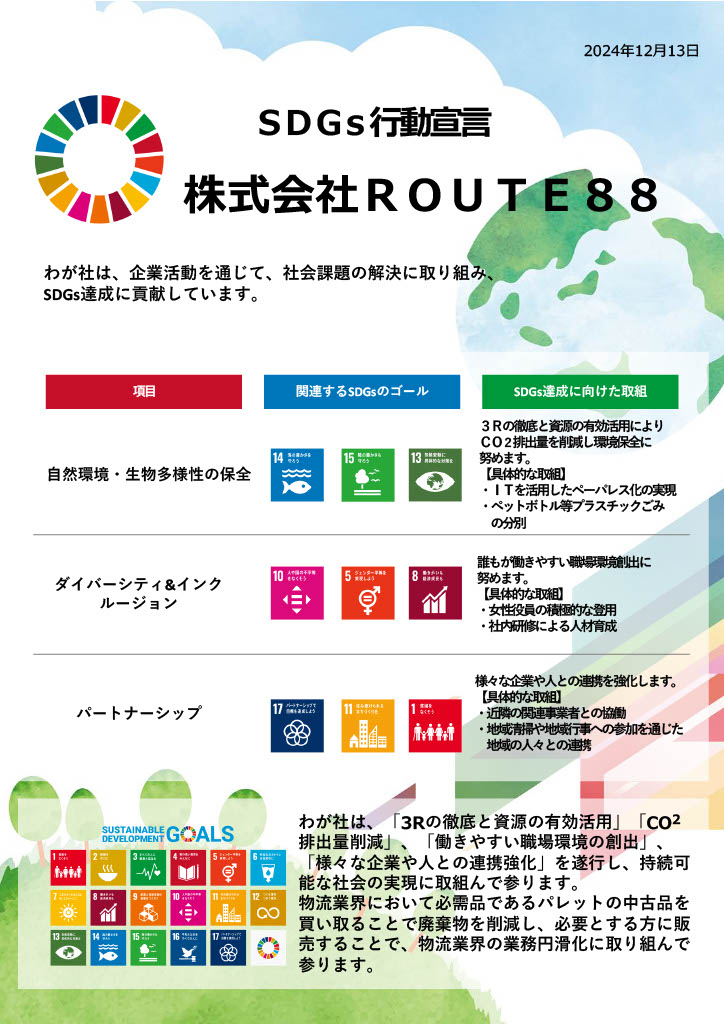数あるパレットのなかでも、ヨーロッパを中心に国際輸送の現場で幅広く活用されているのが「ユーロパレット(EPAL)」です。そもそも、ヨーロッパと日本ではパレットの規格の考え方も異なるため、国ごとに認証マークが違い、厳格な制度を設けている場合もあります。ヨーロッパとの貿易を考えている物流担当者にとっても、ユーロパレットとは何か、日本とサイズが異なる理由についても把握しておかなくてはいけません。ユーロパレットとは何か、不要になったときに買取できるのか詳しく解説していきます。
もくじ
ユーロパレットとは?

ユーロパレット(Euro Pallet)とは、ヨーロッパを中心に世界中で最も広く使用されている交換パレットです。日本以上にヨーロッパではパレットに対して厳格な基準があり、ユーロパレットがなければ物流業界は完全に機能停止に陥ると言われるほど、重要なパレットです。
ユーロパレットの認証を行っているのは欧州パレット協会(EPAL)です。一定以上の基準を満たした企業に対して、ユーロパレットを製造し販売・メンテナンスなど幅広く行っています。ユーロパレットを取り扱う企業の審査も行い、一定の基準を保てるように管理を行っています。
ユーロパレットの基準規格は「1,200×800×144mm」
ユーロパレットの基準規格は「1,200X800mm」「2,000X800mm」が最も一般的なサイズとして認識されています。ちなみに日本の基準規格(JIS規格)は「1,100×1,100」と、ユーロパレットよりもやや小さいことがわかります。また、ユーロパレットとは違い正方形の形をしているため「イチパレ」などの名勝でも親しまれています。
さらに、ヨーロッパの物流現場で使用されているパレットのサイズは、1,200×800×144mm以外にも、2,000×800×144mmの大型サイズもあります。この大型サイズのパレットは、ユーロパレットとは認証されない点は注意して扱う必要があります。
ユーロパレットに記載される2つの認証マークの意味
ユーロパレットは「EPAL」と「IPPC(国際植物防疫条約)」という2つの認証マークが刻印されています。それぞれが認証を与えているパレットであると証明しているものでもあります。ユーロパレットに記載されている2つの認証マークの意味について詳しく見ていきましょう。
EPAL
EPALとは「European Pallet Association」の略称のことをいいます。ヨーロッパ・パレット教会にて認証されていることを認めているものです。EPALはユーロパレットの品質を保証するための認証機関のことであり、ヨーロッパで厳格な基準にて定められています。既定の基準を満たしていないパレットが、EPALの刻印を受けることはできません。
IPPC(国際植物防疫条約)
IPPC(国際植物防疫条約)は、輸出するときに植物に害虫がつき繁殖するのを防ぐ目的を持っています。
具体的には、農作物や植物をはじめ天然資源を対象としており疫病から守る意味があります。185の国で加盟している条約になり、世界的にも認められているものです。
枠組内には「ISPM(International Standards for Phytosanitary Measures)」が定められています。
パレットのなかでも木製のものも条例の対象となるため、輸出で使用する際は燻製処理や熱処理を行い害虫を駆除しなくてはいけません。IPPCのマークがついているパレットは、消毒済みであり国の基準を満たしていることを証明するためのマークです。
ユーロパレットの認証制度の厳しさ

ユーロパレットにて認証を受けるためには、厳格な基準をクリアしなくてはいけません。ユーロパレットの使用は「ボードの数」「釘数」「ブロック数」「長さ」「幅」「高さ」「重量」「安全作業荷重」などのすべてにおいて規定が定められています。これらの規定を満たしていないパレットは、EPAL認証マークの刻印ができず、正規のユーロパレットとして扱われなくなってしまいます。
また、ユーロパレットの交換基準も厳しく定められており、1か所でも欠陥が見られる場合は技術規則に従い、修理をしなくてはいけなくなります。例えば、ボードが見つからないケースや、板の割れ、欠け、釘の柄の露出は修理対象になります。修理は認可を受けた業者以外が対応できないこと、修理を受けたユーロパレットには修理マークがつくなどの決まりもあります。
ちなみに、認可を受けていない業者が修理をしてしまうと、違法となりますので注意してください。
ユーロパレットの認証制度が非常に厳格な理由
ユーロパレットの認証制度が非常に厳格な理由として「等価等枚交換方式(パレットプール)」に基づき、運用されていることが関係しています。そもそも「等価等枚交換方式(パレットプール)」とは、企業間でユーロパレットを貸し借りする方式のことをいいます。
パレットを使用した後は、同じ枚数や同じ品質のパレットを返却しなくてはいけないとしています。例えば、A社が10枚のパレットを受け取った場合、B社に返還するときも10枚の同等規格パレットの返却が義務付けられています。
そのため、ユーロパレットとして規格を統一することによって、効率を高める意味があります。修理や再利用の管理を行き届かせることで、相互性を高めパレットの信頼性を確保しているといわれています。
ちなみに日本から輸出されるときに、ユーロパレットがないときは回収の利便性を高める目的でワンウェイパレットを使い回収しない方法も取り入れられています。
日本におけるユーロパレットの主な活用方法

日本のパレット規格が統一されていないこともあり、国内輸送でユーロパレットを使用する機会はほとんどありません。とはいえ、一切流通していないわけではなく、一部用途によって使われることもあります。
具体的にどのような物流のケースでユーロパレットが使われているのでしょうか。
ヨーロッパ向けの輸出・国際輸送
ユーロパレットは、ヨーロッパ向けの輸出用として使用されています。そのため、取引先がヨーロッパ圏の国際取引を行っている企業にとって、有用なパレットであることがわかります。
家具へのリメイク(DIY)
ユーロパレットは、燻製処理を行い害虫対策を行っていることもあり、虫の発生やカビのリスクが低くDIYに向いているともいわれています。ユーロパレットにIPPC認証マークがついているかどうかで判断できるようになります。
そのため、海外ではリメイクしてベッドやソファのすのことして使われていました。認証マークがついていることによって、他にはないおしゃれな雰囲気を引き出すこともでき、DIY好きな人からも高く評価されています。近年では、日本でもDIYの素材として注目を集めつつあり、ユーロパレットの需要も高まっています。
日本におけるユーロパレットの流通状況
日本におけるユーロパレットの流通は多いとは言えません。国内の物流はJIS規格のパレットが一般的になり、ユーロパレットの流通量は限定されています。現在、ユーロパレットの正規販売ライセンスを種六している日本の認定ディーラーは「日本パレットレンタル株式会社(JRP)」のみとなります。すぐに使用できる、新品のユーロパレットをセットで購入したいという場合は、日本パレットレンタル株式会社に問い合わせて購入するのがおすすめです。
不要になったユーロパレットは買取してもらえる?

企業のなかには、かつてヨーロッパへの輸出を行っていたものの取引が終了したり、規模の縮小や閉業によってユーロパレットが不要になることもあります。「商品のディスプレイ台としてユーロパレットを使用していたが、閉店や改装により不要になった」なんてケースもあると思います。ユーロパレットの買取は基本的には可能と言えますが、業者によっては対応していない場合もあります。そのため、事前に問い合わせをしてから買取に出すかどうかを決めるのを推奨します。また、一般的な日本規格のパレットと比較すると、買取条件がやや厳しくなることも注意しましょう。
ユーロパレットの主な買取条件
ユーロパレットの買取においては、パレットの「状態」が特に厳しくチェックされる傾向にあります。そのため損傷が見られるパレットは、査定額が大幅に下がってしまい、希望通りとは言えません。ひどい損傷の場合は、買取を断られることもあり処分をするためのコストがかさむことになります。追加費用が発生してしまう可能性もあるため、まずはパレットの状態を確認することが大切です。また、買取に出す際にまとまった枚数である100枚以上や50枚以上などの枚数がないと、断られる可能性も出てきます。買取枚数の最小数は業者によっても大きく異なるため、一度問い合わせるのをおすすめします。
ユーロパレットの買取相場
ユーロパレットの買取相場は約200円/1枚(参考サイト参照)と決して高いものではありません。日本国内で見ても、ユーロパレットの需要が全体的に高いとはいえないため、価格が下がってしまうことも考えられます。しかし、ヨーロッパ向けの輸出やDIY・業務用途などのニッチな需要は必ず存在します。ユーロパレットの流通量が多いとはいえないことも相まって、日本で多く流通している木製パレットよりも高値で買取してもらえる傾向もあります。実際に買取に出すときは、複数の業者にて見積もりをもらいましょう。
ユーロパレットの買取の流れと業者の選び方
ユーロパレットの買取の具体的な流れは以下の通りとなります。
5つのステップに従い、買取を進めていきます。
| STEP(1) | 買取業者に見積もり・査定を依頼する |
| STEP(2) | 日程を調整し、現地で査定してもらう |
| STEP(3) | 後日送付された見積書を確認する |
| STEP(4) | 成約後、日程を調整し引き取りに来てもらう |
| STEP(5) | 業者による検品の完了後、代金が支払われる |
ユーロパレットの買取業者を選ぶポイントとして、ユーロパレットの買取を行っているかどうかはもちろん、買い取り実績が豊富で実際にどのくらいの価格で買取しているのかが重要になります。また、買取の対象エリア内であれば、引き取りにきてもらえる可能性もあります。また、なるべく高く買い取ってほしいという場合は、相見積もりをとり、納得できる買取先を選ぶようにしましょう。
ユーロパレットの買取を断られた場合の対処法

最後に、ユーロパレットの買取を断られてしまった場合の対処法を3つ紹介します。
ユーロパレットの処分を考えている人は参考にしてみてください。
納品元企業に引き取りをお願いする
扱いに困ったユーロパレットは、納品先の企業に引き取りをお願いする方法があります。最も単純な方法でもあり、最初に思いつく部分かもしれません。引き取りに費用がかかったとしても、一番手軽な方法とも言えるでしょう。ユーロパレットを処分するときは、まずは納品先に相談してみて下さい。引き取りが難しい時は、他の処分方法を検討してみてもいいと思います。
不用品回収業者・産業廃棄物処理業者に回収を依頼する
ユーロパレットの保管や扱いに困ったときや、早めに処分したいときは不用品回収業者・産業廃棄物処理業者に回収を依頼する方法もあります。一般家庭のみならず、産業廃棄物の回収にも対応していることが多く相談してみてもいいでしょう。ただし、どこの業者でも対応しているわけではなく「産業廃棄物の許可証」を持っている業者に限定されます。処理まで対応してくれる業者を選ぶと、すべての作業をまるごと依頼できるようになります。産業廃棄物処理業者の認定を受けていない業者は、適切な処理が行われず不法投棄のリスクを高めるため注意してください。
解体して粗大ごみに出す
ユーロパレットの量が少なく、企業ではなく一般家庭でDIYの用途で使用していた場合は、解体して粗大ごみとして処分できます。事業用として使用していたユーロパレットになると産業廃棄物に分類されてしまうため、一般ごみとして廃棄すると違法になってしまうので気を付けてください。無料で処分できますが、手間と時間がかかること、解体するときにケガや木くずによるケガのリスクも出てきます。
まとめ
ユーロパレットは、国際的な輸送に欠かせないものでありユーロ圏の輸出を考えている企業にとっても欠かせません。不要になったときは買取や納品先企業へ引き取りの依頼、不用品回収業者・産業廃棄物処理業者への回収などのさまざまな方法があります。ROUTE88でも、EPALの認証を受けたユーロパレットの買取を行なっています。どこに買取に出したらいいか迷っている人は、ROUTE88にお見積もりも含めてご相談いただけますと幸いです。