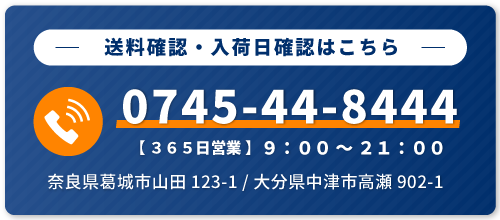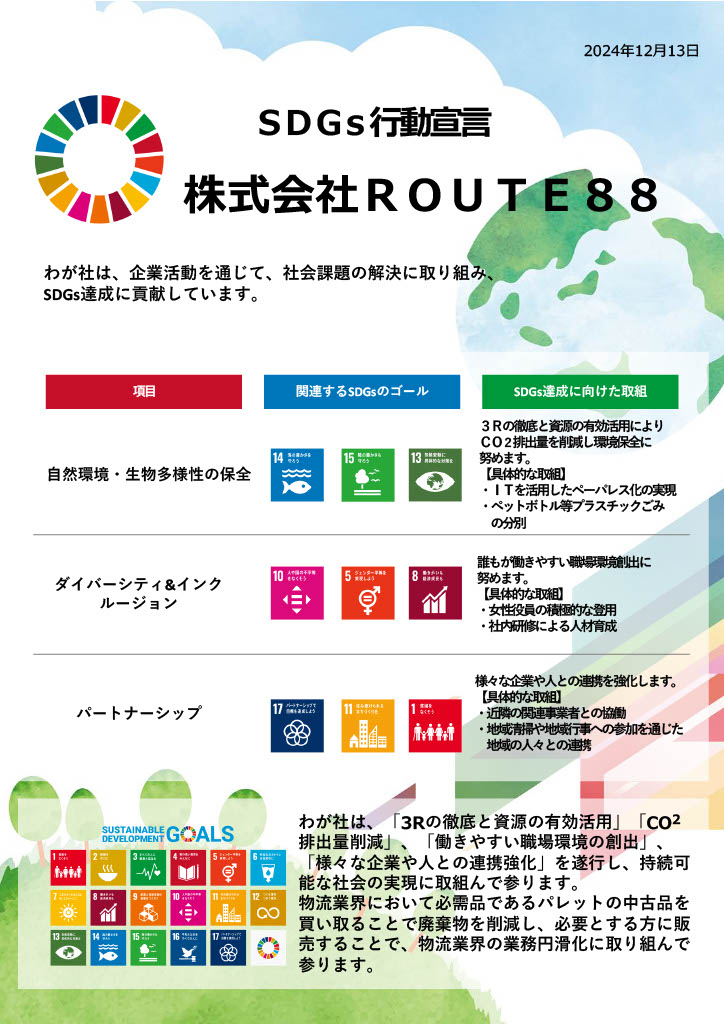もくじ
カゴ台車とは?
カゴ台車とは、格子フレームで覆われているものでキャスターがついているものです。使用している素材や形状にも種類がありますが、スチール製で三面が囲われているものを一般的に多く見かけます。その見た目から「カゴ車」や「ロールボックスパレット」「カーゴテナー」と呼ばれることもあります。
物流業界のなかでも使い方はさまざまで、物を積んでも荷崩れしにくい使用になっており、一度に多くのものを運びたいときや重いものを運びたいときにもおすすめです。販売も行っている施設の場合は、商品の保管や移動にもそのまま使用できます。運搬する時に便利に使いこなせるのもカゴ台車の特徴と言えるでしょう。一般的なカゴ台車は折りたたんで保管できることもあり、コンパクトにまとめて保管できます。
カゴ台車の主な4つのタイプ
カゴ台車の形状には、主に4つのタイプがあります。
それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
標準タイプ
標準タイプは、カゴ台車のなかでも多く見かける形です。3方向の格子もしくは網状に囲まれた状態になっており、段ボールを運び出すときにもよく使われています。荷物の出し入れをするときに、開口部分にサイドバーがついているのも特徴です。荷物の積み下ろしを簡単にして時間を短縮したいと考えている人にとっても、使いやすいと思います。積み下ろしをするときは便利に使いこなせますが、搬送しているときに段差があると荷物が崩れてしまうことも少なくありません。
観音扉タイプ
観音扉タイプは、開口部分に観音開きの扉がついているものです。4方面すべてを柵にて覆うことができるので、段差があるときも荷崩れして落下する心配もありません。扉の部分にはロック機能がついているため、移動距離が長いときでも安心して使用できます。また、観音扉タイプは、扉を左右に開いた状態にするとすべてが開ききった状態になるため、大きな段ボールや荷物の積み込み、荷下ろしなどの作業にも適しています。ただし、カゴ台車の側面にぴったりつけることができないので、すき間が空いてしまいます。
L字折りたたみタイプ
L型タイプとも呼ばれているものになり、底板を持ち上げて左右のいずれかのパネルを折りたたんで使えるタイプになります。折りたたんだときにアルファベットのLのような形状になっていることがL字折りたたみタイプの特徴です。カゴ台車のなかでもスタンダードなタイプになり、使っていないときは重ねた状態で保管しておきます。収納したときも自立した状態なので、使い勝手の良さもある台車です。荷崩れ防止には、バーを使って固定します。
I字折りたたみタイプ
基本的にI字折りたたみタイプはL字折りたたみタイプと似ているものです。より保管効率を高めて安定性を高めたものはI字折りたたみタイプとなります。使っていないときに底板を持ち上げて左右を折りたたむと、アルファベットのIのような形になるので、スペースを取らずにコンパクトに保管できます。バーを使って荷物を固定しつつ維持できるので、さまざまな運搬に使用されています。
カゴ台車を導入するメリット3つ
カゴ台車は、物流拠点だけに限らず店舗などさまざまな場所で使われています。
作業効率を高めたいと考えている人にとっても欠かせないものです。
カゴ台車を導入するか迷っている人向けに、どのようなメリットがあるのか説明します。
荷崩れが起こりにくく安全性が高い
カゴ台車は、3つの面に柵がついており立体的な構造をしています。大量に荷物を運搬するときなど、物品を重ねて積んでいても荷崩れしにくい仕様になっています。多少の段差がある場所を移動したいときにも、カゴ台車は便利に使いこなせます。積み重ねるときのポイントとして、重い荷物を下にして軽いものを上に積むように置くとバランスも維持しやすくなります。より安全に保管し運搬するためには、観音扉タイプのものを選ぶと全面が格子で囲われた状態になるため使いやすくなると思います。
キャスター付きで重量物も簡単に運べる
カゴ台車は、キャスターが付いているため重量物でも簡単に運ぶことができます。カゴ台車によっても変わってきますが、最大500㎏まで積載できるものも多く、小さく重量感のあるものをまとめて移動させたいときにも便利に使えます。積載量に対して軽い力で移動できるのもあり、運ぶのに苦労するようなものでも効率よく運搬できるようになります。男性のみならず、女性でも移動がしやすく作業の負担を軽減できる点も大きなメリットと言えるでしょう。品出し用に使われていることもあり、小回りも良く使いやすいのもカゴ台車の特徴です。
未使用時はコンパクトに収納できる
カゴ台車は、未使用時にコンパクトに収納できるのも特徴です。サイドバーを外して底板を上げると柵を折りたたんで保管できるようになります。コンパクトで場所を取りませんし、限られたスペースしかない人にとっても保管に困りません。複数台使っている場合も、圧迫感がないため必要なときに組み立てるなど調整しやすい点も、カゴ台車の良さと言えるでしょう。
カゴ台車導入における3つのデメリット
カゴ台車の導入には多くのメリットがありますが、いくつかのデメリットも存在します。
カゴ台車にはどんなデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。
バラ積みと比べて積載効率が低下する
カゴ台車のデメリットとして、車両に積載できる台車数が決まってしまうことです。同じように運搬する時に使用するバラ積みと比較すると、積載効率が下がってしまうため使いにくさを感じる部分もあります。また、異形物のように積み重ねが難しいものの場合、カゴ台車での移動に適していない場合もあります。積載するものが限られてしまうため、慣れていないと使いにくさを感じることもあると思います。
作業環境の整備コストが発生しやすい
カゴ台車は事前に作業環境を整備するためのコストがかかります。積み込みや積み下ろしなど人が行うのが難しく、専用の装置などが必要になります。トラックにテールゲートリフターや昇降装置などを、搭載してカゴ台車を問題なく使えるように調整する必要があります。他にもドックレベラーという荷台とセンターの床の高低差を調整することで、積み込みに対応できるようになります。設備コストの調整コストをどこまでかけられるかも重要になってきます。
事故発生リスク低減に向けた安全対策が必要となる
カゴ台車は、事故発生リスクもないとはいえません。例えば、キャスターがついているため転がしながら効率よく移動ができますが、カゴ台車そのものに重量感があります。誤って足を轢いてしまうと、大けがをしてしまうリスクも高まります。特に段差や傾斜のある場所では、スピードがでないように慎重に作業を行う必要も出てきます。他にも、高く積みすぎてカゴ台車が倒れてしまったり、人や物に衝突することも考えられます。事故発生リスク低減にむけた、安全対策をしっかりと行うようにしましょう。
カゴ台車の安全性と利便性を高めるオプションパーツ
カゴ台車の利便性を高めたいと考えているのであれば、オプションパーツを取り付けるのをおすすめします。オプションパーツにもさまざまな種類があるため、そのなかでも特におすすめのものを紹介します。
中間棚
カゴ台車の中間部分にとりつけて段数を増やすためのオプションパーツです。積み重ねが難しい荷物を運搬するときにも、中間棚を使うと複数の荷物を同時に運べるようになります。カゴ台車には最大3枚の中間棚を取り付けることができ、運ぶ荷物によって気軽に調整できます。耐荷重は最大500㎏と耐久性のあるカゴ台車ですが、中間棚は100㎏以下と制限があるため乗せる荷物を選ぶ必要があります。
保冷カバー
保冷カバーは、カゴ台車にとりつける温度上昇を防ぐためのオプションパーツです。主に冷蔵庫からの荷物を運搬させるときに使用するものです。生鮮食品を移動するときに短時間であっても荷物が傷んでしまうのを防ぐ効果が期待できます。特に夏場に荷物を移動させるときにも重宝します。遮熱性や遮光に優れており、高い保冷効果が期待できるものです。装着も簡単なので必要なときに気軽に取り付けて使用できます。
防塵カバー
カゴ台車に取り付けることで、荷物に雨やホコリが付着するのを防ぐオプションパーツです。運搬しているときはもちろん、荷物を保管しておくときに汚れ防止対策としてもよく使われています。段ボールは水に弱いので、雨に濡れてしまうと強度が著しく下がってしまいます。濡れたあとに乾燥させても、強度がもとに戻ることもありません。できるだけ濡らさないようにするためにも防塵カバーを使いましょう。
カゴ台車の選び方|チェックすべき4つのポイント
最後に、カゴ台車を選ぶ時のポイントを4つ紹介します。
どのカゴ台車にするべきか迷っている人向けにチェックするべきポイントを紹介します。
(1)サイズ
カゴ台車を選ぶうえで、最も重要になってくるのが最適なサイズかどうかです。運搬する荷物に適したサイズや耐荷重のカゴ台車を選ぶようにしてください。大きなカゴ台車を選べば運べる荷物の種類も多くなり、使用用途も広がります。ただし、エレベーターのなかや店舗のなかなど狭い道を通るときは、大きなサイズのカゴ台車だと使いにくくなってしまいます。用途に合わせて適切なサイズのカゴ台車を選ぶようにしてください。実際によく使う通路の幅を測ってから、カゴ台車を購入するのをおすすめします。
(2)底板の材質
カゴ台車の底板には「樹脂製」と「スチール製」の2種類があります。樹脂製は、軽くさびにくい素材になりますが、頑丈さはやや物足りなさを感じます。そのため、荷物に割れた天板の破片が混入してしまう可能性も考えられます。スチール製は、やや重さやありさびやすい素材になりますが、樹脂製よりも頑丈な仕様でできています。どのような荷物を運ぶのかによっても変わりますし、使用場所や環境に適した底板のカゴ台車を選ぶようにしましょう。
(3)キャスターのタイプ
カゴ台車のキャスター部分は「Aタイプ」と「Cタイプ」があります。Aタイプは、2輪が固定されているものになり左右に移動できるキャスターです。車輪が安定していることもあり、走行にぶれもありませんし、使いやすいキャスターです。Cタイプは4輪のすべてが動くキャスターになるため、柔軟に移動しやすく動かしやすいのも特徴です。やや走行が安定しにくいデメリットもありますが、小回りもききますし狭い通路でも使いやすいカゴ台車です。
(4)費用
カゴ台車を新品で購入した場合、約3万円~8万円と幅があります。中古で購入した場合、約1万円~5万円と新品よりもやや安い価格帯になります。カゴ台車を導入してみたいと考えているものの、実際にどのくらい使用するのかわからず使い勝手を見てみたいと考えている人もいると思います。低コストで導入するためには、中古品の購入もしくはレンタルをおすすめします。
掲載先のサイトでは、カゴ台車の取り扱いがあるため一度覗いてみてください。
→ カゴ台車
まとめ
カゴ台車は、荷崩れが起こりにくく運搬にも適しています。
使わないときは折りたたんでコンパクトな状態にして保管できるので、限られたスペースでも十分に活躍してくれます。
ただし、慣れていないとケガなどの安全性のリスクや調整コストもかかってきます。
実際にカゴ台車を使ってみて、運搬する商品に適しているかどうかを判断してみてもいいと思います。
カゴ台車はこちらにもたくさん掲載しています。参考にしつつ最適なカゴ台車を選ぶようにしていきましょう。