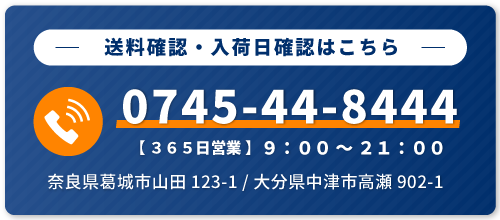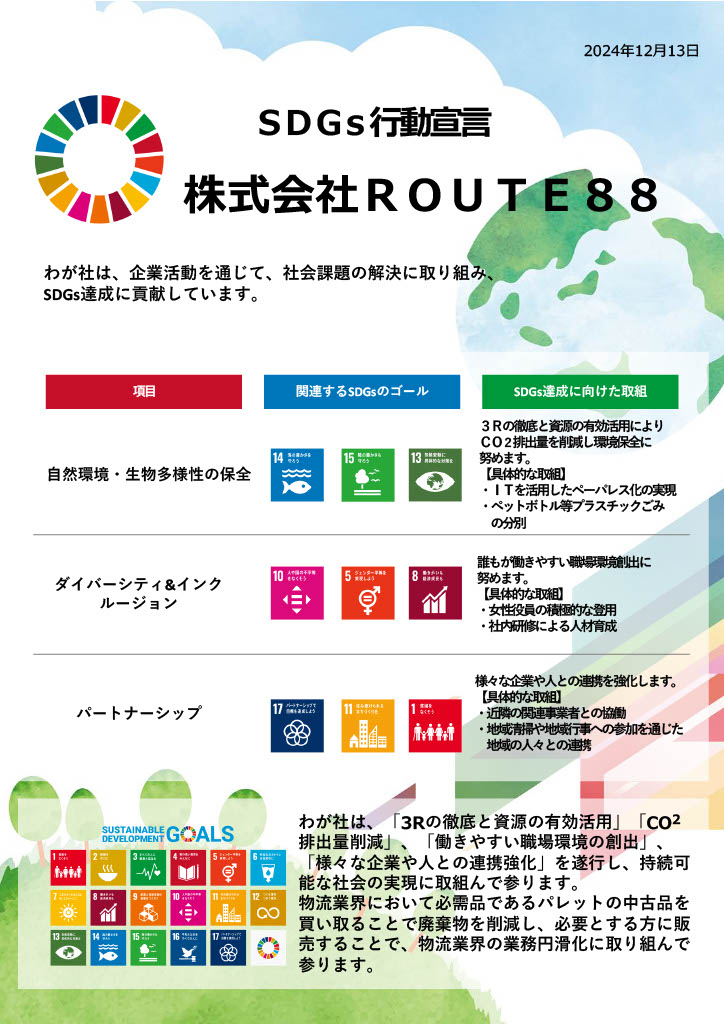物流倉庫で、荷物を積み上げて保管するときによく見かけるのがネステナーです。
名前の呼び方も多く、仕様もさまざまなので、どれを導入するべきか迷っている人もいるのではないでしょうか。
荷物をパレットごと保管したいときにも使えますし、そのままフォークリフトにのせて移動させることも可能です。
作業効率を高めたいと考えている人にとってもネステナーは便利です。
ネステナーとは何か、メリットや注意点、選び方のポイントなど詳しく説明したいと思います。
もくじ
ネステナーとは?
ネステナーとは、物流の倉庫や工場などでよく使われている保管用のラックです。スチール製の頑丈な仕様のものになり、パレットとセットで使用されるのが一般的です。ネステナーは、「ネスティングラック」「ネスラック」「スタックテナー」「テナー」などさまざまな名前で呼ばれていますが、いずれも同じものを指しています。ネステナーは背が高いものほど、耐荷重が低くなるのが特徴です。
ネステナーは、臭能力を向上させるために使用するもので、凹凸がついておりフォークリフトを使ってはめ込むことで段を重ねて利用できるのも特徴です。ネステナーを使うと、段ごとのパレットの取り出しも簡単になりますし、スムーズに移動できるようになります。平置きよりも立体的だからこそ、下にあるパレットの取り出しも簡単です。
ネステナーの主な種類2つ
ネステナーは、大きく分けて「正ネステナー」と「逆ネステナー」の2種類に分類されます。
それぞれどのような特徴があるのか、詳しく見ていきましょう。
正ネステナー
正ネステナーは、荷物を置く部分が下についているタイプです。荷物を置いたままでネステナーごと、フォークリフトを使って移動できます。ネステナー単体だと、物品を通常のパレットのようにしか保管できない仕様になっています。都度、荷物を降ろす必要がなくトラックにそのまま載せることもできます。倉庫のレイアウトを頻繁に変更したいと考えている人にとっても、正ネステナーは使いやすいと思います。季節によって取り扱う商品の大きさや種類が変わる場合でも使いやすいのが特徴です。
逆ネステナー
逆ネステナーは、正ネステナーを反対にしたような形状をします。
物を載せる格子が上に位置していることもあり、重ねて使用することで2カ所に荷物を載せることができます。最下部に置く方法と上部に置く方法があるため、保管できる荷物の量も多めです。限られたスペースのなかで、より多くの荷物を保管したいと考えている人にとってもおすすめです。また、天井が低い倉庫など使用出来るネステナーが限られている場合でも、逆ネステナーであれば問題なく使えます。フォークリフトの移動には向いておらず使用できません。使う用途によって、正ネステナーと逆ネステナーのどちらがいいのかを決めるようにしましょう。
ネステナーを導入する魅力・メリット3つ
ネステナーを導入するうえで、どのような魅力やメリットがあるのでしょうか。
組み合わせによってスペースを有効に活用できる
倉庫のなかにネステナーを導入することで、商品の保管効率を高めることに繋がります。組み合わせによって、限られたスペースを有効活用できます。例えば、必要に応じて3段や4段に積み上げた状態で保管できるので、保管効率を高めたいと考えている人にもおすすめです。なかでも、季節によって保管する物品の量が変わるような企業にとっても、柔軟に調整できるのもあり活躍してくれるでしょう。
レイアウト変更の柔軟度が高い
ネステナーは床に固定されていないため、正ネステナーであればフォークリフトを使って簡単に移動できます。トラックを使い積み込みできることもあり手軽に移動できる点も大きなメリットと言えるでしょう。倉庫内で置く場所を限られてしまうこともなく、必要に応じてレイアウトを変更できます。倉庫を保管用途以外に使いたいと考えている人にとっても、柔軟度の高いネステナーは便利に使いこなせます。
未使用時はコンパクトに収納できる
ネステナーは未使用時は積み重ねたうえでコンパクトに保管することが可能です。倉庫の場所をとる心配もありませんし、ある程度ストックとして置いておけるので荷物の量に合わせて使い分けができます。保管効率に影響を与えることもありませんし、コンパクトだからこそたくさんのメリットが期待できます。
ネステナー導入における注意点
ネステナーにはたくさんのメリットがありますが、導入するうえで覚えておきたい注意点もあります。
ネステナーにはどのような注意点があるのか、詳しく見ていきましょう。
内寸を超える長尺物は積載できない
ネステナーは高さが調整できないため、内寸を超えてしまうような長尺物を積載することはできません。これは支柱部分に連結場所がなく1本状態になっているためです。ネステナーの内寸よりも高さのある物品は別の方法で保管しなくてはいけなくなります。ネステナーを積み上げたいと思っても、天井の高さによっては難しい部分もあるでしょう。保管する物品によっても適切なネステナーを選ぶ必要があります。
高く積み上げると安定性が低下する
ネステナーは保管効率が高いため高く積み上げて使いたいと考えている人もいるでしょう。スペースこそ少なくなりますが、高さが出ればでるほどバランスが悪くなってしまいます。特に、上部に重いものを置いていると、ちょっとしたバランスの崩れによって大きな事故に繋がる可能性も考えられます。地震のような揺れにも弱いので、倒れてしまうリスクをいかに防ぐにはどうしたらいいのか考えなくてはいけません。
耐震対策を含む安全対策が必要となる
高く積んでバランスが悪くなったときに、耐震対策を含めどのような安全対策を行うのかが重要になってきます。耐震性に優れたネステナーを導入するのも一つの方法ですし、ちょっとした対策もあります。バランスが崩れ転倒しないように、重いものを下に載せる方法もおすすめです。また、隣り合うネステナーを連結して、崩れないように工夫をする方法もあります。地震に限らず、衝撃によって崩れる恐れがあるからこそ、しっかりとした安全対策を行うようにしましょう。
ネステナーとパレットラックの違い
ネステナーに似ている物流機器に「パレットラック」があります。
それぞれの違いがわかりにくいと感じている人もいるでしょう。
ネステナーとパレットラックの違いについてまとめてみましたので、参考にしてみてください。
| パレットラック | ネステナー | |
|---|---|---|
| 特徴 | 高く積み上げやすいメリットもありますが、設置に費用がかかる | 段積みしやすく作業に適したメリットがある。ただし、輸送に適していない |
| サイズの違い | W2500×D1100(積載面) | W1230×D1150(積載面) |
| 高さの違い | 調整できる | 調整できない |
| 収納のしやすさ | 設置してしまうと解体や移動がしづらく場所をとってしまう | コンパクトに収納したうえで移動することも可能 |
| 荷崩れのリスク | 比較的安定している | 専用のストッパーを使う必要あり |
| 耐震性のリスク | 柱が座屈してしまう可能性もある | 耐震性の高さにも定評がある |
それぞれ似ているように見えるネステナーとパレットラックにも大きな違いがあるのがわかると思います。
季節によって荷物の量が変わるときは、ネステナーのように柔軟性の高いものがおすすめです。高さのある荷物を収納するのであればパレットラックのほうが柔軟に対応できます。それぞれ目的に合わせて選ぶようにしてください。
ラックパレットについて、以下でも紹介しています。
→ ラック パレット
ネステナーの利便性をより高めるオプションパーツ
ネステナーの利便性を高めるためには、オプションパーツを取り付けるのをおすすめします。
オプションパーツにも種類があるため、迷っている人向けにおすすめを4つ紹介します。
連結金具・バンド
ネステナー同士もしくは柱を固定するためのオプションパーツです。耐震性を高めるのはもちろん、揺れを軽減させて倒壊を防ぐ効果が期待できます。フォークリフトがぶつかってしまったときにもずれを防ぎ、安全性を高めることにも繋がります。金具とベルトの両方があり、より強固に固定する場合はベルトタイプを選ぶのをおすすめします。自由度が高くサイズ調整ができるベルトタイプになるので自分にあったオプションパーツを選ぶようにしてください。
飛び出し防止クランプ
ネステナーは、荷物が飛び出してしまうのを防ぐためにクランプを使います。ネステナーが揺れたときにパレットがずれてしまい、外にはみ出てしまうこともあります。揺れが大きいと荷物が落下してしまい、故障の原因となったり安全な作業といえなくなってしまいます。できるだけ揺れを少なくするためにも、パレットの落下を防ぐ目的で、飛び出し防止クランプを使います。
フォークガイド
ネステナーを運搬する時に、フォークリフトがズレないようにするためにフォークリフトに取り付けます。フォークリフトのときに動いてしまうと、バランスを崩す原因となってしまいます。ズレた状態になると設置や段積みを行うのが難しくなってしまいます。都度、調整をする手間もかかってしまうので、できるだけずれを防ぐためにも、フォークリフトを使うようにしてください。
中棚
中棚は、ネステナーの本体に追加して収納性を高めるために使用します。デッドスペースをなくして、棚を追加することでスペースの有効活用にも繋がります。また、本体にパレットを置くための台を追加して収納性を高める方法もあります。自由な取り付けができるのもあり、収納スペースを上手に活用しつつ使うためのオプションパーツを選ぶようにしましょう。
ネステナーを選ぶときのポイント
最後に、ネステナーを選ぶ時に覚えておきたい4つのポイントを紹介します。
(1)サイズ・高さ
ネステナーのサイズを決める時は、保管する荷物から逆算して決める必要があります。日本の標準サイズとして定められているのはイチイチパレットと呼ばれる「1100×1100×144mm」に対応しているものです。JIS企画にて「T11型」として規格化されています。日本で使用されているコンテナとの相性もいいため、さまざまな業界で使われているサイズ感です。国際物流にも適したサイズ感としてもおすすめです。
(2)耐荷重
ネステナーの耐荷重は、1段1000㎏が一般的です。積み重ねた状態でも使えますし、ネストップを使い、最大3000㎏まで載せることも可能です。ただし、高さが2mを超えるようなネステナーの場合は、500㎏程度の耐荷重になるため、少し制限がかかってしまいます。ネステナーに何を保管するのか、必要な耐荷重はどの程度になるのかを計算したうえで、ネステナーを導入するようにしてください。
(3)積み上げ方式
ネステナーの積み上げは、「上ピンタイプ」「下ピンタイプ」「レールタイプ」のなかで選択できます。例えば、上ピンタイプは、上部の過度に2㎝程度のピンが飛び出しているものになり、凹凸部分を合わせて積み上げていきます。レールタイプは、噛ませて積み上げていくなど、方法にも違いがあります。同じ積み上げ式のネステナーを選ぶようにしましょう。
(4)最大積み上げ枚数
ネステナーの高さによって積み上げられる段数の目安が決まっています。例えば、ネステナーが1m前後の場合は4段まで積めますが、2m以上になると2段積みが限界となります。倉庫の天井の高さによっても変わりますし、何を保管するのかによっても変わってきます。積み上げる数は、安全に使用するためにも過剰にならないように決められた数を守るようにしましょう。
(5)価格
ネステナーは、新品で17,000円~、中古で15,000円~と相場も変わってきます。銅の価格が高騰していることもあり、以前よりも新品の価格も高くなっています。中古の場合、新品よりも費用を抑えつつ購入できるので、コストを抑えたいと考えている人にもおすすめです。ただし、中古の場合はネステナーの状態を確認したうえで選ぶようにしましょう。
まとめ
ネステナーは、限られたスペースのなかで積み上げ有効活用できるのはもちろん、レイアウトの柔軟性が高く、コンパクトにまとめて収納できるなどの良さもあります。ただし、積み上げたときにバランスが悪くなってしまうこともあるため、オプションパーツを使うなどの工夫をしておきましょう。また、乗せる荷物の種類や重さ、段数や方式なども含め、価格的にも満足できるネステナーを選びましょう。
また、ネステナーをお探しの方はこちらも参考にしてください。